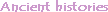非日常的高揚
気がつくと、わたしは血の混じった水の流れに四つん這いになっていた。
そのうち弟と従兄弟が、近くの小学校から保健の先生(養護教諭)を連れて走ってきた。
その先生は、びしょ濡れのわたしの服を脱がせ、代わりに毛布をくれた。
思い出してみると、その日、従兄弟二人が遊びにきて、どこへ行くというわけでもなく、一緒に自転車にのって出かけた。
前を走る従兄弟が両手離しで乗っているのを見て、わたしも調子に乗って自分のママチャリのハンドルから両手を離した。道路は直線で、順調に走っていた。
ところが、ペダルをこぎ始めるのとほとんど同時にわたしの自転車はバランスを崩した。あわててハンドルを握ろうとしたが、立て直すことはできず、道路横の農業用水路(幅約60センチ、深さ約70センチ)に落ちた。といっても落ちたところの記憶はない。
わたしは、なにかうれしいことがあると怪我をすることが少なくない。
無意識のうちに舞い上がっているのだろう。
〜・〜 〜・〜 〜・〜
怪我をするとか恥ずかしい行動をとってしまうかどうかは人それぞれだろうが、ほとんどの人は日常のちょっとした変化をけっこう楽しんでいるのではないだろうか。事実、変化がなければ生きるのもつらい。
「大型で強い台風が北北東に進み、明日の未明には東海地方に上陸する見込み。」
なんていう気象予報士の言葉を聞いたら、わくわくしてしまう人がいる。
日本道路公団ハイウェイラジオでは、
「東京方面へ走行中の方へ。xyzキロポスト付近を頭に、下り線(反対車線)の事故を見物する車で流れが悪くなっています。」
などという道路情報を聞くことがある。
近所で火事があると、野次馬のみならず、ビデオカメラまで持っていく人もいるらしい。
それらはみな、祭りのようなものである。自分に害がなければなおさらのことである。
〜・〜 〜・〜 〜・〜
あるとき、コンビニにお弁当を運んでくるトラックが2台来た。2台が同時にくるのを見たのは初めてだった。
ドライバーの一人が、あわただしく、「ばんじゅう」といわれるトレイを弁当6段、焼きたてのパン2段重ねて運んできた。いつも11時26分までには届くはずが、かなり遅れていた。
「事故で遅れてるのかねえ。」
と店員Yと話していたところだった。
ばんじゅうの数はだいたいいつもどおりだが、彼はうれしそうで、とてもはりきっているようにみえた。店を出ると、もう一人のドライバーが、北のほうを指差し、「あっち?」と聞いているようだった。それにうなずくと、バタバタと車に乗り、二台は走リ去った。普段の彼はお弁当を運んでくるドライバーの中でも一番おとなしそうで、あいさつも元気のない人だった。そのときはまるで別人のようであった。
その事故と言うのは東名高速道路の事故で、大きな荷物が下を走る国道1号線に落下したというものだった。
高速は渋滞で、国1は通行止め。それを知らずに高速の渋滞を避けて国1に向かう車で、両道路のアクセス道路はとてつもなく混んでいた。パトカーも出動してスピーカーで迂回路を知らせていた。
わたしはそのアクセス道路の渋滞に巻き込まれたので、弁当を運ぶ人はどうするんだろうと考えていたのだった。
なぜ2台で来たのか、通行止めで流れないところのコンビニにはどうするのか、忙しいドライバーに聞けるはずもなかった。
ただ、忙しいけれども自分の懐には関係のないドライバーとすれば、祭りのようなものでしかなかったのだろう。そう感じてしまうような顔をしていた。
〜・〜 〜・〜 〜・〜
「いままで生きてきた中で一番幸せです。」
いままで生きてきた中で、とキーボードを打っていたら思い出してしまった。それだけで本文とはあまり関係ありません。
今まで生きてきた中で、一人だけ、真剣な人を見て驚いてしまったことがある。
わたしが過去に勤めていた会社は富士山一合目(標高約1000メートル)にあり、そこは霧が出やすく、雷の落ちやすい位置のようだった。
夏のある日、大雨だった。雷もすごかった。あちらこちらで雷が落ちているような音が聞こえた。避雷針に落ちるものもあったようだ。
コンセントにさしてあるプラグはすべて抜いた。電気が伝わって危険らしい。
約2km伸びている監視カメラのケーブルはとっくにやられている。
そのうち、火災報知器がけたたましく鳴った。
非常用放送からはサイレンが鳴る。止めようとしても止まらない。
報知器の示す発報地は二箇所。別棟である。雷が激しく、外へ出られなかった。
雨雷ともに少し落ち着いた。所長は祭り好きらしく、外へ出たかった。職員一人を連れて発報箇所を点検に行ってしまった。
サイレンを聞きつけ、近くの施設のおばさんが二人、軽自動車に乗ってやってきた。車を停め、事務所に向かって歩いてこようとしている。
わたしと同僚は玄関に出た。
彼女たちは、まだ遠く、
「何かあった?」
と大声で聞く。数十メートルは離れていた。
わたしは、玄関でニコニコしていた。実は、楽しかった、あるいは嬉しかったのである。台風で学校が休みになったときの小学生のようなものである。みんなそんなものだろうと思っていた。
ところが、である。わたしの隣に立っていた同僚は違っていた。
「来るな〜!車から降りちゃダメー!」
と、マジで怒鳴っている。怒っているのではなく、その場の危険を真剣に感じ、本気で彼女たちのことを心配していたのである。
わたしはあっけにとられ、叫んでいる同僚の横顔を驚きの表情で見ていた。
どうしてこれほど真剣になれるのだろう。信じられなかった。
でも彼は素晴らしい人だと思った。それに、間違いなく例外と呼ぶにふさわしい人だと思っている。
やはり自分に危難のおそれがあったとしても、異常事態は祭りと同じである。たとえ彼のような人がいたとしても、わたしはそう考える。